「ISO17100」とは?翻訳の品質を守る 国際規格をやさしく解説!~翻訳よろず相談室~
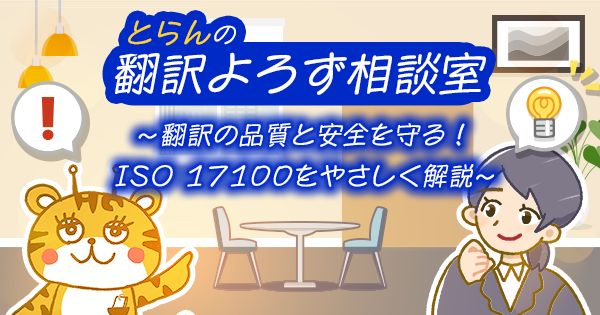
Index
翻訳にも国際規格(ISO規格)があることをご存知ですか。
翻訳サービスに関する国際規格「ISO17100」とは、高品質な翻訳サービスを提供するために求められる各種要件を規定したもので、2015年5月に発行されました。
今回の「とらんの翻訳よろず相談室」では、この「ISO17100」についてお客さまによくご質問いただくことをピックアップして解説します。

実は、翻訳センターは「ISO17100」の策定にも関わっていたんだって。
今回は、そんな「ISO17100」の誕生秘話も紹介するよ。
【ご相談1】どの翻訳会社に依頼しても、翻訳って同じ?
お客さまから、よくいただくご相談を紹介します。
「どの翻訳会社に依頼しても、翻訳って同じなの?」

実は、翻訳工程は翻訳会社によって違うことがあるよ。
そこで、「ISO17100」の規格ができたんだ。
「ISO17100」とは
「ISO17100」は、翻訳サービスのプロセスを国際的に標準化するために制定された規格です。
この規格では、品質の高い翻訳サービスを提供するために求められる各種要件や翻訳者の資格要件や作業プロセス、管理の方法などが具体的に定義されています。
「ISO17100」が規定する代表的な要件:
- 翻訳者の資格や専門性
- 翻訳とチェックの分離(ダブルチェック体制)
- プロジェクト管理の手順
- 顧客とのコミュニケーション体制
詳しくは、翻訳センターの「品質管理の取り組み」ページにも記載しています。
「ISO17100」の翻訳区分
「ISO17100」の翻訳区分は、下記の5つがあります。
翻訳区分:
- A金融・経済・法務
- B医学・医薬
- C工業・科学技術
- D特許・知財
- Eその他
翻訳センターでは、上記の中でもA,B,C,Dの区分の認証を取得しています。
詳細は下記のページからご覧ください。
ちょっとコラム:「ISO17100」の誕生を振り返る
ここで「ちょっとコラム」です。
私たち翻訳センターは「ISO17100」規格の認証を日本で最初に取得しました。
そして、「ISO17100」の誕生そのものにも関わっています。

それって、どういうことなのかな?
当時を知る人にインタビューしてみたよ!
お話を聞いた人:田嶌さん
田嶌さんは2002年の入社以来、一貫して品質管理と業務プロセス改善に携わっています。
担当者インタビュー(国際規格誕生の舞台裏)

翻訳センターが日本代表として「ISO17100」の誕生に関わったっていう話は、
とらんも聞いたことはあったんだけど、具体的にどんなことをしたの?

日本を代表して国際会議に参加し、
他国の代表者たちと規格に盛り込む内容を議論しました。
会議の開催国が毎年変わるので、
規格が固まるまでにスペイン、南アフリカ、ドイツと旅をしましたね。
もちろん、プロジェクトリーダーから事前にドラフトが提供されますが、
各国からさまざまな意見が出されて、会議の場で次々と修正を入れていきます。
自国の利益がかかっているので、みんな必死です。

国際規格となると、色んな国で議論が行われるんだね。
日本から参加したのは翻訳センターだけだったの?

はい、議論が始まった2012年は当社だけでした。
当時、経済産業省から日本翻訳連盟(JTF)に
『日本の翻訳業界を代表してどなたか会議に参加してくれませんか』という
お話がきたのですが、詳細も分からない、渡航費用もかかる、という状況でした。
そこで、当時のJTF会長だった前社長が、
日本が国際的に取り残されてはならない、と
日本代表として当社が参加する決断をしたんです。
その決断がまさか自分に降りかかってくるとは思いもしませんでしたね。

最初はやはり手探り状態だったんだね。
「ISO17100」の誕生までで一番大変だったことは?

一番大変だったのは、
欧州など、翻訳学の学位を取得できる国が多いのに対して、
当時日本では翻訳を学べる教育機関は存在するものの、
翻訳学の学位を取得できる大学・大学院が存在しなかったんです。
もし、学位が要件に含められたら日本は完全に不利になるという状況の中、
要件を緩和するよう、必死で他国の人たちを説得しなければならなかったことですね。
責任の重たさに押しつぶされそうでした。

田嶌さんの説得で、要件の緩和を勝ち取ったんだね、アメイジング!
最後に、現在「ISO17100」は、国内の約60社の翻訳会社が取得しているね。
この状況はどう思う?

取得している会社が増えたことは嬉しいですね。
ただ、今の規格の内容は機械翻訳やAI翻訳が
世に広まる前に制定されたものなので、
正直、そのあたりの考慮が不足していると感じています。
それでもなお、翻訳プロセスの基本が
しっかりと盛り込まれた有用な規格だとも思っています。
ポストエディットの国際規格「ISO18587」が別で存在しますが、
その規格との整合性を維持しながら、
そう遠くない将来、現状に合わせた改訂が入る可能性があると見ています。
引き続き、動向を見守る必要がありそうです。

そうなんだ、「ISO17100」の今後が、ますます気になるね。
お話を聞かせてくれてありがとう!
【ご相談2】多言語の場合は?
次にご紹介するのは、こちらの質問です。
「多言語の翻訳を「ISO17100」準拠で依頼したい。翻訳センターではどの言語の「ISO17100」を取得しているの?」

翻訳といえば、まず日本語と英語間を想像するけど
ヨーロッパ言語やアジア言語への翻訳もあるよね。
多言語も「ISO17100」に適合
翻訳センターでは、日英・英日だけでなく多言語に関する「ISO17100」の認証も取得しています(2025年3月に追加取得)。
これは、特定の多言語に限定されたものではなく、日英以外の言語でも「ISO17100」の要件を満たしていることを示しています。
「翻訳する言語でプロセスが変わるの?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的な工程は多言語翻訳も日英翻訳と変わりません。
希少言語であっても、翻訳者の選定やチェック体制など、品質管理には十分な注意を払って対応しています。
「ISO17100」の認証証(にんしょうしょう)
「ISO17100」を取得している翻訳会社では、品質へのこだわりを示すために、認証証を自社WEBサイトに掲載しているケースが多く見られます。もちろん、翻訳センターもWEBサイトで認証証を公開しています。
【ご相談3】ポストエディットやAI翻訳の場合は?
最後のご質問です。
「機械翻訳(MT)やAI翻訳の修正を依頼する場合でも、国際規格に適合した翻訳プロセスで対応してくれるの?」

機械翻訳の後のチェックはポストエディット(PE)と呼ばれていて、
ポストエディット案件には翻訳サービスとは異なる国際規格があるんだよ。
ポストエディットの国際規格とは
近年、機械翻訳(MT)やAI翻訳の技術が進化し、それらを活用した翻訳の依頼も増えています。
ポストエディット(PE)とは、機械翻訳やAI翻訳の出力結果を人間が確認し、必要な修正を加える作業を指します。
翻訳センターでも、ポストエディットサービスに対応しています。
ちなみにポストエディット(PE)は、前章でご紹介した「ISO17100」の適用対象ではありません。
ポストエディットには別の国際規格である「ISO18587」が存在します。
「ISO18587」の要件の代表的なものは、下記のとおりです。
- ポストエディターの資格や専門性
- ポストエディットの作業手順と品質管理(プロジェクト管理の手順)
- 顧客とのコミュニケーション体制
なお翻訳センターは、「ISO18587」に関しては認証機関による認証ではなく、「自己適合宣言」による対応をしています。
「ISO17100」の認証証と同様、「自己適合宣言書」も翻訳センターのWEBサイトでご覧いただけます。
※自己適合宣言:自社で規格の要求事項を満たしていると判断し、その適合を社内外に対して宣言すること
まとめ
いかがでしたか?
翻訳は、ドキュメントの内容や目的に応じて最適な対応が求められる「オーダーメイド」のサービスです。
翻訳センターでは、翻訳者やポストエディターが国際規格で定められた要件を遵守し、お預かりした大切なドキュメントにふさわしい翻訳を丁寧に仕上げています。
「どの翻訳会社に依頼すればいいのか迷っている」という場合は、「ISO17100」の認証取得の有無を確認したり、どういったプロセスで翻訳しているのかなどをヒアリングしたりするのもおすすめです。
皆さまのご希望に適した翻訳がお手元に届くように、まずは翻訳会社に相談してみてください。
※当社が提供する翻訳またはポストエディットサービスのすべてが「ISO17100」または「ISO18587自己適合宣言」に準拠しているわけではありません。ISO適合が必要な場合は、依頼時に担当者までお申し付けください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
翻訳センター ブログチーム

とらんちゃん
「とらん」だけに「トランスレーション(翻訳)」が得意で、世界中の友達と交流している。 ポケットに入っているのは単語帳で、頭のアンテナでキャッチした情報を書き込んでいる。
- 生年月日1986年4月1日(トラ年・翻訳センター創業と同じ)
- モットー何でもトライ!
- 意気込み翻訳関連のお役立ち情報をお届けするよ。
New
新着記事
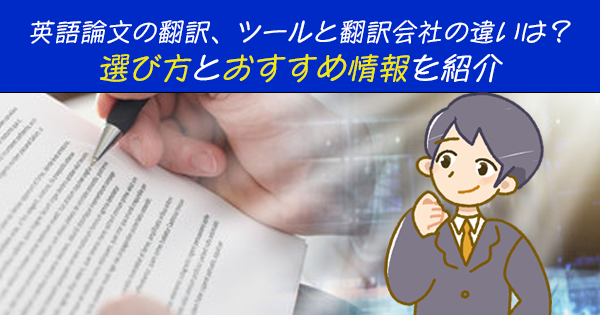
2025.12.24
- 翻訳あれこれ

2025.12.10
- お役立ち
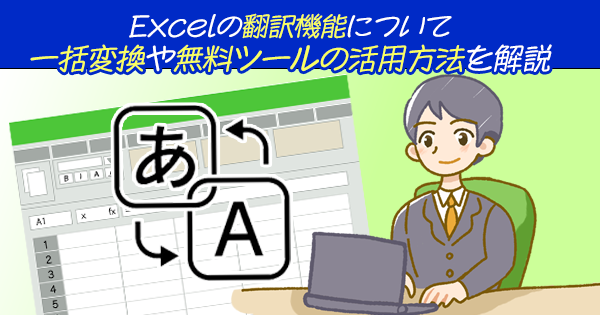
2025.11.26
- お役立ち

2025.11.12
- お役立ち
お問い合わせ窓口
(受付時間:平日10:00~17:00)
新規のお問い合わせ、サービスについてのご質問など、お気軽にお問い合わせください。



